

この記事に書かれていること
犬がケージで吠え続ける時の対処法
 ケージに入った状態の犬が「ワンワンワン!」と連続で吠え続けているのが困るというご相談をよくいただきます。
ケージに入った状態の犬が「ワンワンワン!」と連続で吠え続けているのが困るというご相談をよくいただきます。
ダメ!と言っても吠え続けるし、ご近所の迷惑になるのでどうにか吠え止ませたいと思って、ついケージから出してしまうケースも多いかと思います。
お気持ちは非常にわかるのですが、ケージで吠え続けるのをやめさせるためにケージから出してしまうという対処は、将来的に無駄吠えをする犬にしてしまう恐れのある方法です。
あとで犬がケージで吠え続ける理由と、その場合の対処法もご紹介しますが、小手先の対処法だけだと吠え止むまでに時間がかかったり、上手く吠え止ませられないこともあります。
普段の日常から愛犬をある程度飼い主さんがコントロールできるようにしておく必要があるんですね。
それも踏まえて、犬がケージで吠え続ける時の対処法ですが
- しつけをして信頼関係を築く
- 犬の気持ちや習性・犬の学習のしかたなどを理解する
愛犬がケージで吠え続けているとしたら…もう少しスピードアップをさせてしつけに取り組んでもらう必要があるかもしれませんので、それぞれを見ておきたいと思います。
ケージで吠え続ける時の対処1:しつけをして信頼関係を築く
 犬がケージで吠え続けている場合は吠えないことが正しい行動だとしつけで教えてあげる必要があります。
犬がケージで吠え続けている場合は吠えないことが正しい行動だとしつけで教えてあげる必要があります。
犬をしつけるということは、犬に人間社会のルールを教えて、犬が人間社会でストレスを感じることなく快適に生活ができるようにしてあげるために行うことです。
そして、飼い主さんは犬にとって安心して頼れる存在であって、「飼い主さんの言うことに従っていれば危険なこともなく守ってもらえる」と思ってもらえるように教えていくことでもあります。
犬は群れで生活をしていたころの名残から、子犬の時にまわりの存在に順位をつける時期があるため、一緒に住んでいる家族全員に順位をつけていると考えられていました。
「犬に下に見られるな」とか「犬と上下関係が逆転している」という表現を聞いたことがあるんじゃないでしょうか?
犬よりも下に見られないように上下関係をしっかり築くという考え方はもう古くて、現在は世界的にも犬とは信頼関係(正しい主従関係)を築くことが大切という考え方になっています。
脅しや恐怖によって犬を支配することはできます。
犬に厳しくして、怒られたら怖いことを教え、逆らったら痛い思いをさせられるという認識にさせることで犬は言うことを聞くようになるでしょう。
現在でもこのような考え方で犬を訓練する訓練士も実際にいらっしゃいます。
- 目を見つめながら叱りなさい
- 犬より上の目線で生活をしなさい
- 主人より前にご飯を食べさせてはいけない
- 子犬でも厳しく接しなさい
このようなアドバイスをされる訓練士は、古い考え方の可能性が高いです。
 家族として迎えて、家族として生活をしていくパートナーとしての犬に対して、恐怖で従わせるような方法ってどうでしょう?
家族として迎えて、家族として生活をしていくパートナーとしての犬に対して、恐怖で従わせるような方法ってどうでしょう?
もちろん犬が正しくない行動をしたら叱ることもありますが、根本的なところが違っています。
また、一生懸命しつけをしようとしてコマンドを教えているけど「芸」を教えているのと同じになってしまっている飼い主さんもいらっしゃいます。
ごはん前の待てだけはできるけどあとはやらないとか、コマンドをかけた時「やるときもあるけどやらないときもある」という場合は、正しくトレーニングができているのではなくて芸になってしまっている可能性が高いです。
犬は信頼する飼い主さんからの指示には、自分のしたいことよりも優先して飼い主さんの指示に従います。
大好きな飼い主さんの指示に従うことは、犬にとって喜びでもあることです。
 このような状態になると、飼い主さんが「ダメ」などの禁止用語を使った時も「いけないこと」だと判断してすぐ辞めるようになります。
このような状態になると、飼い主さんが「ダメ」などの禁止用語を使った時も「いけないこと」だと判断してすぐ辞めるようになります。
信頼関係を築く前に、一生懸命いけないことを教えようとして「ダメ!」と言われる飼い主さんがたくさんいらっしゃいますが、この時点でダメを教えようとしてもなかなか犬には伝わりません。
ケージで吠え続けている犬に対して、信頼関係も築けていない状態で、しつけも進んでいなければ、犬に何を言っても吠えることをやめないのは当然のことです。
じゃ信頼関係を築くのはどうしたら良いのかというと、信頼関係を築きやすいトレーニングを行うことが最短の方法になります。
信頼関係を築きやすいトレーニングってどんな方法?と思われたら「イヌバーシティ」というしつけ教材の方法が一番おすすめです。
他にもしつけ教材というものはありますが、あまりおすすめできないと思える内容のものばかりでした。
でもイヌバーシティに関しては、私も多くのご相談者様におすすめをしてきましたが、みなさん「手にして良かった」「もっと早く実践したかった」と言っていただくくらい大好評です。
ですが、いくら良いと勧められても「イヌバーシティってうちの子に必要なのかな?」と思われるでしょうし、そもそもイヌバーシティを実践するメリットがいまいち感じられないかもしれません。
そのような方に、イヌバーシティを実際に実践した飼い主さんからいただいた感想やどのように愛犬が変わったのか、実践するメリットをご紹介している記事がありますので、一度ご覧になってみてください。
愛犬の行動にお困りだった飼い主さんからの生の声をたくさん載せてありますので、あなたの愛犬がどのように変わるのかイメージしやすいと思います。
 関連記事
関連記事
ウソみたいにお利口さんになる特別な秘訣を大公開です!
ちょっと強力過ぎじゃない!?見違えるほどお利口になるしつけ方法があるの?
トレーニングの方法というのは、訓練士さんによっていろいろな方法があります。
たくさん犬にトレーニングをしていくうちに、効果の高い方法や、犬がわかりやすい方法など訓練士の技量や経験によって編み出される部分が多いです。
イヌバーシティのトレーニング方法は多くの飼い主さんと迷える問題犬たちを救ってきた実績のある方法で、驚くほど短い時間で愛犬との関係が劇的に変わりますので、子犬であったらなおさら早くから取り組んでもらいたいと思います。
イヌバーシティはいっさい体罰を使わずに、最短時間で愛犬と信頼関係を築くことでしつけをスピードアップする方法です。
古いしつけのように、犬に厳しくしたり上下関係を気にすることなく、愛犬から信頼され、愛され、頼りにされるしつけ方法ですので、安心して実践していただけます。
もちろん吠えている犬に対する対処も解説されていますし、何より正しい方法だと自信を持って行ってもらうことができるので、飼い主さんのしつけに対するストレスが大幅に軽減されることが最大のオススメ理由です。
先ほどの記事をご覧いただくとお分かりいただけますが、イヌバーシティの方法でしつけをした犬がどのように変わるのかをご覧いただけます。
もの凄く吠え続けていた犬もピタッと吠えるのがおさまっています。
犬に伝わりやすい正しい方法で教えてあげれば、犬は理解し吠えるのをやめますし、飼い主さんの指示にも喜んで従うようになります。
できるだけ早いうちから信頼関係を築く正しいトレーニング方法を実践していただくことで、色々なしつけもでき、他に出始めている困った行動等も自然と直ってお利口さんな犬にしてあげることができますのでぜひ一度先ほどの記事か公式サイトをご覧いただきたいと思います。
公式サイトの方にも、イヌバーシティを実践した場合
- 犬がどのように変わることができるのか?
- どれくらいのボリュームがある教材なのか?
- どんなことができるようになるのか?
- どんな人が作ったものなのか?
- 実践した人はどのように思ったのか?
- 各コンテンツの内容
などがすべて書かれているので、納得してから手にすることができます。※他のしつけ教材は手にするまでどんな内容なのかわからないものも少なくありません。
ケージで吠え続ける時の対処2:犬の気持ちや習性・犬の学習のしかたなどを理解する


犬を飼ううえで、これは理解しておいてほしい部分ですが、意外と多くの飼い主さんが犬についてあまり理解を深めていない状態で飼われているのをお見受けします。
ですから、どうしても人間目線で犬の気持ちを推測してしまったり、犬にわかりにくい方法で教えようとしてしまいます。
例えば、犬を叱ったあとに犬が反省しているように見える時ってありますよね?上目がちに飼い主さんの様子を見ながらしょんぼりしているように見えるやつです。
あれは反省しているわけではなく、これから起こることに不安を感じていて、とても緊張している状態です。
犬は過去のことにさかのぼって、自分の行動を振り返ることはできません。
自分が経験したことから学習をすることはできますので、過去のことを忘れるわけではありませんが、過去の行動を振り返って反省することはないんですね。
目の前で恐ろしい顔をしながら怒っている飼い主さんの顔から、「これからどうなるんだろう」「早く興奮がおさまってくれないかな…」と思っているので、反省ではなく極度に不安を感じている状態です。


犬の気持ちや習性などを踏まえたうえで犬に「してほしい行動」「正しい行動」を教えていかないと、犬は正しい学習ができずに、してほしくない行動を学習してしまいます。
ペット先進国の欧米では、犬を飼う前に講習を受けて犬についての理解を深めたり指導の仕方を知ってから飼うことが義務付けられている国などがあります。
本来は日本でもそういった講習を受けてから犬を飼い始めてもらうと、犬を「問題行動を起こすような犬」に育ててしまう危険を防げますが、何も知らない状態で犬を飼い始める飼い主さんが多いです。
犬が吠えることは犬のコミュニケーションの一つでもありますから吠えることを禁止するのは酷なことですが、必要以上に吠える必要がないことを教えるのは飼い主さんの責任です。


ここで犬の気持ちや習性を理解できていないと、正しく伝わらないか、間違えた学習をさせてしまう可能性が高くなってしましまいます。
ケージなどで吠え続けるのも同じことが言えます。
吠えている犬に対して「うるさいから静かにしなさい!」と犬に負けないくらいの声で犬に注意したとします。
すると、犬は「飼い主さんも大きな声を出しているぞ!僕ももっと頑張って大きな声を出そう」と思って吠えが悪化している可能性もあります。
犬の気持ちや習性を理解していないために、伝えたいことが伝わらずに、犬に間違った行動をさせてしまっているのがお分かりいただけると思います。
親切なしつけ教室や、信頼できるしつけ教室になると、講習や座学として犬に対する理解を深められる講義をしてくれるところもあります。
ここら辺はネットで探すなどの独学で学ぼうとするのは危険です。
必要な情報といらないもの、正しい情報と間違った情報が混在しているのがネットですから、できれば犬のプロから正しい情報を得ていただきたいと思います。
でも、
- これだけのためにしつけ教室に行くのは面倒
- そもそも講習があるしつけ教室が近くに無い
- 時間がなくてしつけ教室に通うことがむずかしい
イヌバーシティはコンテンツが大変豊富なのでボリュームがあり過ぎるとお感じになるかもしれませんが、お手持ちのスマホで視聴することが可能ですので、通勤や家事などの「ながら時間」や「すきま時間」でご視聴いただけます。
さらに何度も見返すことができるので知識の定着もしやすく、実践中はスマホを見ながら実践することができるので間違えるなどの心配もありません。
犬を飼うということは、犬も飼い主さんも日々の生活を楽しく愛情いっぱいのものにする必要があります。
そのためには、犬に関する環境をきちんと整えてあげないと、あとで吠え癖に悩んだり噛み癖がついて悩みが深刻化する可能性が高いです。
まだ、直すことができる今の状態を少しでも早く改善して、これから長く続く愛犬生活を幸せなものにしてもらうお手伝いになれると思うので、イヌバーシティをご検討いただければと思います。
私もここまで強くおすすめするからには、あなたに少しでもお得に手にしていただけるよう特別な特典をご用意させていただこうと考えました。
私のおすすめを信じてイヌバーシティをご購入していただいた方には、イヌバーシティをより効率よく実践できるよう、しほ先生との対談音声を無料特典としてプレゼントさせていただきます!※この特典は今後終了する可能性があります。
対談音声では、教材には書かれていない
- 効率よく訓練するために気を配ると良いこと
- 犬の性格によって褒め方を変えると良い理由
- 犬が楽しくなる訓練方法とは
- 体罰以外に絶対にしちゃいけないこと
- しつけでうまくいかないときにすると良いこと
愛犬家のみなさまにとって、効率的にしつけができるようになる「虎の巻」といった内容になっています!
せっかくならここでしか手に入らない特典がついた今、イヌバーシティをご検討いただきたいと思います。
※本サイト内のどのリンクをタップしていただいても特典がつくように設定しています。
犬がケージで吠え続ける理由と具体的な対策


しつけが進めば、そもそもむやみに吠えることは少なくなり、信頼関係が築かれるほど犬は飼い主さんが喜ばない行動を判断できるようになるので、自分から吠えようとしなくなります。
特に、何らかの要求を通そうとして犬が吠え続ける場合は、犬が悪いのではなく飼い方を間違えてしまっている可能性が高いです。
これから犬がケージで吠え続ける理由をご紹介しますが、まずあなたの愛犬がどういう理由で吠えているのか正しく見極めないと対処を間違えてしまいます。
この見極めが外れてしまうと、どんなに練習をしたり対処をしてもほとんどの場合うまくいかないので注意してください。
犬がケージで吠え続ける理由として考えられるのは
- 要求
- 恐怖
- 威嚇
- ストレス
1つ1つ詳しく見ていくその前に…
まずケージを見直してみましょう。
見直すポイントは、ケージの広さとケージを設置している場所です。
- 周りが気になって仕方ない環境になっていないか
- 気に入らない場所に設置していないか
- 広さは適切か
ケージは犬が最も落ち着いていられる場所にする必要があります。
特に子犬であれば、旺盛な好奇心があるため、周りが気になってしまって「外に出たい」という気持ちを強くしてしまいます。
この場合は、ケージごとタオルケットなどで覆って周りを見えなくしてしまうか、クレートをハウスにすることがおすすめです。※クレートについてもイヌバーシティで詳しく解説されています。


ただ中の温度が上がってしまうのだけは気をつけてください。
また、ケージが廊下などの人の通りが激しい場所や、落ち着かない場所に設置していないかも確認してもらいたいと思います。
犬は聴力も嗅覚も人間より優れているので、人間では気がつかない嫌な音が聞こえていたり、嫌なにおいがしている可能性もあります。
ケージの場所を変えただけで吠えなくなる場合もあるので、思い切ってケージの場所を移してみるのも一つの方法です。
あと、ケージの広さは広すぎても犬は落ち着けません。
このことを考えても、体の大きさにあったクレートでゆっくりと休める環境を作ってあげるのがおすすめです。
それでは、ケージも適切な状態にできたということで、それでも吠える理由についてみていきます。
犬がケージで吠え続ける理由1:要求
- ケージから出してほしい
- 散歩に連れていってほしい
- 遊んでほしい
- お腹がすいた など


これらの要求によって吠えている時は、生活のリズムがいつも決まっていると吠えやすくなります。
犬も体内時計で、お散歩に行く時間とかご飯を食べる時間が分かってくるので、わざと生活リズムを乱してご飯やお散歩の時間を大幅に変えてみてください。
変える時は、吠える前にしたいため時間を前倒しで、吠える前に行動するようにしてください。
ケージから出しても良い場合は、吠え続けている状態で出してしまうと、吠える=ケージから出られるという成功体験から間違った学習をしてしまいます。
ケージから出す前に、「フセ」などのコマンドを出し、それに従えたら「フセ」ができたことを褒めてから出すようにすると、出たくなったらフセをして待てるようになります。
オスワリでも良いのですが、フセの方が興奮がおさまる効果があります。


お散歩とは別で、飼い主さんも何かをやりながら片手間に遊ぶのではなく、飼い主さんもアクティブに動きながら犬のことだけに集中して楽しく一緒に遊ぶ時間です。
意外と「勝手に遊ばせている」とか、「おもちゃを与えて好きにさせている」といった飼い主さんが多くて、中には「お散歩に連れていっている時間が遊ぶ時間だと思っていた」という方もいらっしゃいます。
毎日必ず犬と楽しく遊ぶ時間を作っていくことで、飼い主さんのことが大好きという気持ちを育むことができますし、精神的にも遊んでもらったという満足感を得られます。
犬との遊び方というのは本当に大切なので、イヌバーシティでは一つのコンテンツとして深堀されています。
犬がケージで吠え続ける理由2:恐怖
- 1人で心細い・不安を感じる
- 嫌な音やにおいがする
- 怖いものが近くにある
- ケージによい印象を持っていない など


罰として長時間閉じ込めたことがあったり、まだお留守番の訓練もできていないのに長時間お留守番をさせたなども大きな不安となります。
掃除機をかける音に向かって吠え続けるのは、掃除機の音が怖かったり、掃除機の動き方が不規則なため恐怖を感じている可能性があります。
無理矢理ケージに入れたことがあったり、罰やお仕置きとしてケージを使ったことがあると、犬はケージに良い印象を持てなくなります。
ただでさえ、大好きなご主人の傍にいられなくなるのがつらいと感じているかもしれません。
嫌な印象があるケージに入れられるということは、それだけで恐怖を感じることです。
罰やお仕置に使ったことは無いのに、ケージに入れると吠えるとおっしゃる方も少なくありません。
その方によくお話を伺うと、飼い主さんがお出かけをするときだけケージに入れておくというケースもありました。
ケージに入ることが、飼い主さんのお出かけ・独りぼっちのお留守番など、ネガティブなイメージを持ってしまっていることが考えられます。
このように、飼い主さんが気付かずにケージに嫌なイメージをつけていることもありますので、ケージやハウスの使い方は間違えないように飼い主さんが理解しておくことも大切です。
恐怖により吠え続ける場合の対策としては、恐怖の対象がわかればまずそれを取り除くようにしてください。
あと、正しい方法でクレートトレーニングをして、クレートは安心して過ごせる空間だということを教えます。
クレートに入ったときは縄張りを監視しなくても良いし、吠える必要がない安心していられる場所だと覚えさせ、クレートにいる間はゆっくりと休憩時間だと思えるようにします。


クレートに入ることを嫌がるようだと、どうしても入っていないといけない状況になったときに、愛犬の寿命を縮めるほどストレスがかかる恐れもあります。
正しくクレートトレーニングができれば、そんなに長い時間が必要な訓練にはなりませんし、犬にとっても辛いトレーニングにはならないはずなので、ぜひすぐにでも取り組んでもらえればと思います。
正しいトレーニングについては、イヌバーシティがお役に立てると思います。
>>イヌバーシティ公式サイトをご覧になる場合はこちらをタップしてください
>>実践者の声やメリットをご確認したい方はこちらをタップしてください
犬がケージで吠え続ける理由3:威嚇
- 誰かを追い出したい
- 侵入を知らせたい
- 落ち着かない
生後6,7か月あたりと言えば、まだまだ子犬だと思われるでしょうが、精神的な成長で言えば人間の中学生後半くらいだと考えてもらうとわかりやすいと思います。
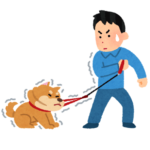
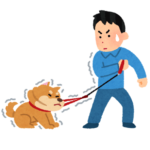
チャイムの反応して吠え続けたり、来客に向かって吠え続けるということも出てきます。
また外の影響を受けて、早朝のバイクの音やお散歩の足音などに反応して吠えることもあります。
威嚇に対する対策は、正しくしつけをして吠えなくて良いことを教えるのが一番だと思います。
それに加えて、窓の近くや玄関の近くなど外の影響を受けやすい場所にケージを置かないようにしたり、守るべきテリトリーを小さくしてあげるなどが効果的です。
これにもクレートは必須アイテムです。
適切な大きさで安心していられるケージであればケージでも問題ないですが、要はテリトリーを狭くしてあげることで警戒すべき場所が狭くなります。
よく、お留守番中に全部の部屋に入れるようにして、自由に動き回れるようにしておいてあげるという飼い主さんもいらっしゃいますが、それだと全部の部屋が守るべきテリトリーになってしまいます。
警戒しなきゃいけない範囲が広いため、犬はずっと緊張して警戒をしていなきゃいけないんですね。
でも、ここに犬の居場所としてクレートを置いておいてあげることで、犬のテリトリーはクレートだけになるので、クレート内で安心してお留守番をすることができます。
「広い場所で自由に動き回りたいだろう」という飼い主さんの優しい心配りだと思いますが、犬を理解していないことで知らずに犬にいらない負担をかけていたり、警戒心を強くするような生活をしてしまっているといえます。
犬がケージで吠え続ける理由4:ストレス
- 環境が変わった
- サークルの中が退屈
- 運動不足
- 愛情不足 など


環境が大幅に変わったことによるストレスから吠えるようになってしまったことが考えられます。
正しいしつけをして信頼関係が築けていれば、一時的なことですぐにおさまります。
環境の変化に不安も感じたかもしれませんが、頼りになる飼い主さんが傍にいてくれるという安心感を取り戻すので、環境が変化した時は少し愛犬と過ごす時間を長くしてあげると良いでしょう。
ケージより広めなサークル内で遊ばせているという方もいらっしゃると思います。
その場合は、サークルの中に噛んでも壊れないようなおもちゃを入れておくようにしてください。ただそのおもちゃもずっと同じだと犬も飽きてしまうので、色々と変化をつける工夫が必要になります。


あとにおいがついているガムやおやつが入る知育玩具なども、夢中になるので時間が稼げるアイテムになります。
お散歩ではリーダーウォークができていることも大切です。
犬がリードを引っ張って前へ前へ行こうとするお散歩だと、運動になるどころかストレスを溜めるお散歩にしてしまっているかもしれません。※リーダーウォークのトレーニングやお散歩とストレスについてもイヌバーシティで解説されています。
ストレスによって吠える場合はストレスの原因を取り除くことが重要なので、普段の生活を見直してみて、何がストレスになっているのか考えてみてください。
ケージで吠え続ける犬に無視は間違い?


でも、知らずにしてしまっている飼い主さんの行動や、間違えた飼い方によって吠える犬にしてしまっている可能性は非常に高いです。
ケージで吠え続けている犬に対して犬が悪い・バカな犬だと思ってしまうこともあるかもしれませんが、それは大きな勘違いで、ちゃんと吠える必要が無いことを教えてあげれば吠え続けることは無くなります。
これはしつけの方法が間違えている可能性があり、飼い主さんが犬に「正しい行動」を伝えられていないために犬は不安になったり警戒したりして吠え続けていると考えられます。
吠え続けてしまうことをただの無駄吠えとしてとらえられてしまっては、犬もかわいそうと言えるんですね。
多くの飼い主さんは頑張ってしつけをされていると思います。
ただしつけの方法を間違えてしまうと、ケージで吠え続けるだけではなく他にも色々な問題行動があらわれてくるようになるので、本当にしつけの方法というのは重要になってきます。


確かに、「無視をする」というしつけはありますが、無視のしかたを間違えてしまうと犬に増大なストレスを与えてしまい、そのストレスから問題行動に繋がるケースが出てきてしまいます。
犬が飼い主さんに対して不信感を感じてしまい、大切な信頼関係を壊してしまうと、他にできていたはずのしつけもできなくなったり、一向にしつけが進まないという負のループに入ってしまいかねません。
無視をするときの注意点としては
- 無視をすることが正しい対処法であるケースなのかを間違えない
- 正しい方法で完璧に無視をする
- 家族の全員で考え方や態度を一致させておく
- 諦めやすい状況にする
これらのことがありますが、たいてい無視をし始めると犬は気付いてもらおうとしてさらに声が大きくなったり吠え方が激しくなったりします。
こうなった時、飼い主さんが正しい無視のしかたをしていると自信を持って行えていないと、根負けをして吠え止ませる行動をとってしまいます。
イヌバーシティでは、吠えている犬を吠え止ませるために正しい行動の伝え方や無視のしかたなどもコンテンツとして解説されていますので、信頼関係を築きながら吠え止ませることができるようになります。
「イヌバーシティって良さそうだけど…うちの子に必要なのかな?」と、少しでもイヌバーシティにご興味を持っていただけたら、実際に実践した飼い主さんからいただいた感想や、実践するメリットをご紹介している記事を、一度ご覧になってみてください。
愛犬の行動にお困りだった飼い主さんからの生の声をたくさん載せてありますので、あなたの愛犬がどのように変わるのかイメージしやすいと思います。
>>実践者の声やメリットをご確認したい方はこちらをタップしてください
ケージで吠えている犬にしてはいけないこと


ストレスからイライラする日常を送られていることでしょう。
しかし、ケージで吠えている犬にしてしまうと、吠えを悪化させるか、最悪の場合は吠える以外の問題行動(噛むとか威嚇するようになる)を起こさせてしまうかもしれません。
吠え続けている犬にしてはいけないことは、先ほどご紹介したようにやみくもに無視をすることのほかに
- 叱る・声をかける
- 無駄吠え防止グッズを使う
などがあります。
吠え続けている犬に対して天罰方式で驚かせると一時的に吠え止むことはありますが、根本的な解決にならないですし、音に慣れてしまったらまた吠えだすようになるので、してはいけないとは言いませんが難しい部分があるのは確かです。
叱る・声をかけるというのがいけないことはなんとなくご想像いただけると思いますが、無駄吠え防止グッズというのは意外かもしれません。
無駄吠え防止グッズの全てを否定しているわけではありませんが、無駄吠え防止グッズの中でも首輪に電気が通ってビリビリさせるタイプのご使用は安易に行うのは危険です。
きちんと装着しないと意味がないというのもありますし、きちんと装着すると放電部分が犬の首の皮膚にずっと当たることになるので皮膚炎を起こし、ただれを起こして重症化するケースもあります。
また、びりびりと電気が通ったことに驚いた犬がパニックを起こして、それに驚いた飼い主さんが首輪を外そうとしても暴れたり噛みついて外せないというケースも聞いています。
無駄吠え防止グッズを使えば犬が吠えなくなるという考えだけで使用すると、犬との信頼関係を壊してしまいますので、やはり根本的な解決を実践していただく方が良いと思います。
犬がケージで吠え続ける~最後に


犬がケージで吠え続ける理由や対処法についてみてきましたが、やはり大切なのは犬に対する理解を深めて人間の考え方で考えないことと、正しいトレーニングをしながらしつけをして信頼関係を築くことです。
犬に何かを教える時は、犬がするべき行動をわかりやすく教えることが必要です。
言葉で伝えられない犬に、してほしい行動を教えるというのは少しコツがいるんですね。
あと、「吠えるからその対策」とか「噛むからその対処法」といったように、しつけは細切れで考えるものではなく、トータルで知って行うことが全体のしつけの成功やしつけのスピードに大きな影響を与えます。
しつけは1つ1つ教えていきますが、相乗効果があるものなので、正しく行うことができれば驚くほど早くいろいろなしつけができるようになります。
そして、お利口犬になれます。
でも、1つ1つの方法を独学で、ネットなどで調べながら進めてしまうと、相乗効果にならずに、下手をしたら相性の悪いトレーニングを組み合わせてしまって、しつけが一向に進まないことも多いです。
これだけ情報があふれているんだからと、ネットで調べられる飼い主さんが一番引っかかる落とし穴です。
最初から、どんな時期にどのようなトレーニングをして、何ができるようになっていれば良いのかを知って、効果的なトレーニング方法で犬を導いてあげられたら、犬も混乱することなくすぐに覚えることができます。
ぜひ、正しいしつけの方法を知って実践していただければ、吠えることも噛むこともないお利口さんな犬に育ててあげられます。
愛犬との生活が楽しく幸せなものになることを切に願っております。



